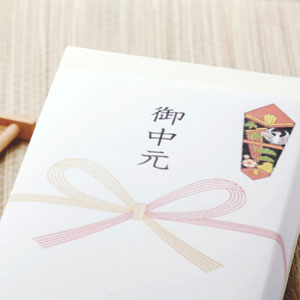
お中元のお返し
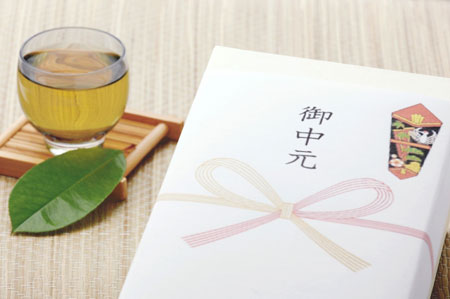
お中元を頂いたときに考えてしまうのがお返しのこと。お中元のお返しは必要ないと聞きますが、貰っておいて何もしないのも気がかりです。もしお返しをする場合は頂いた品物の金額に対していくらぐらいのお返しが相場なのでしょうか?またその際の熨斗の表書きはどのように書くのがいいのでしょう。そこでお中元のお返しのマナーについてご紹介します。
お中元のお返しは必要?それとも不要?
お中元のお返しは必要なのでしょうか。
お中元は日頃の感謝を込めて贈りますが、いざ頂いた場合には相手に気をつかわせてしまったと申し訳なく思ってしまいます。
お中元の品物を頂いたお返しを真っ先に考える方も多いのではないでしょうか。
しかし本来お中元はお世話になっている方に日頃のお礼や感謝の気持ちを伝える意味のものです。必ずお返しする必要があるわけではありません。
お中元はお返しをしなくてもマナー違反ではないのです。
でも頂いたままというのも気がかりですよね。
そこでお中元を頂いた場合は相手の心遣いに感謝して、すぐにお礼状を書いて送ります。両親や兄弟など身内の場合は電話でもいいでしょう。
お礼状の文面のポイントは、お中元を受け取った報告と頂いたお礼を書くといいでしょう。
お中元を受け取った際のお礼状はできるだけ早く送るのが礼儀
お中元を贈った先方は無事に届いたか心配されているでしょう。お礼状が届けば品物を受け取ったことや喜んでいることもわかりますので一安心です。お返しはしなくてもマナー違反ではありませんが、お礼状を出さないのはマナー違反です。
お中元のお返しの金額の相場はいくら?
お中元のお返しは必要ないと思っても、相手によってはお返しを検討した方が後々良い場合もあります。
それはお中元を贈ってくれた相手がお返しをするのは当然と思っているような場合です。このような場合はお返しの必要はないと割り切らずに臨機応変に対応した方が良さそうです。
また他にも相手によっては、むしろこちらの方からお返しの品物を贈りたいと思うようなお付き合いの方もいるかもしれません。そのような場合はお返しの品物を贈ったとしても差支えはありません。
ではお中元のお返しをする場合は、頂いた品物の金額に対してどのぐらいの品物を贈るのがいいのでしょうか。
お中元を贈る場合の金額の相場は、およそ3,000円から5,000円ぐらいです。このような品物を受け取った場合は、同程度の金額の品物を贈るのがいいでしょう。
逆にお返しとして頂いた品物よりも明らかに高価な品を贈ると、先方に失礼にあたります。
お中元のお返しの熨斗の表書きはどうすればいい?
お中元のお返しをする際に注意したいのが熨斗の表書きです。
お返しを贈るタイミングによっても表書きは変わりますので確認しておきましょう。
具体的には関東地方の例でご説明します。
関東地方はお中元を7月15日までに贈りますので、お返しは7月15日前後からになります。
その際のお中元のお返しの熨斗の表書きは以下のようになります。
関東地方のケース
| お返しを贈る時期 | 熨斗の表書き |
|---|---|
| 7/15頃まで | お中元 |
| 7/15以降~8/7(立秋頃)まで | 暑中御伺または暑中御見舞 |
| 8/7以降~8/末頃まで | 残暑御見舞 |
このようにお中元の時期を過ぎた場合のお返しの表書きは「暑中御見舞」や「残暑御見舞」になります。
※お中元を頂いた際のお返しは同様にお中元とはしないで、少し時期をずらして暑中御見舞や残暑御見舞とする方が良さそうです。
また関西地方などお中元を贈る時期が8月15日までという場合は、8月15日までは「お中元」それを過ぎたら8月末頃までは「残暑御見舞」とします。
まとめ
お中元を頂いたら、できるだけ早くお礼を伝えましょう。
身内であれば電話やメールでも大丈夫なこともありますが、一般的にはお礼状を送ります。
お礼状は遅くなるとタイミングを逃してしまい、送りづらくなってしまいます。
忙しくても丁寧に書いてできるだけ早く送りましょう。
またお中元のお返しは本来必要ありませんが、それでもお返しを贈る場合、品物は同程度の金額のものを選びます。
お返しの熨斗の表書きはお返しを送る時期によっても変わりますので、気をつけておきましょう。
お中元を通じて良い関係を続けていきたいですね。





