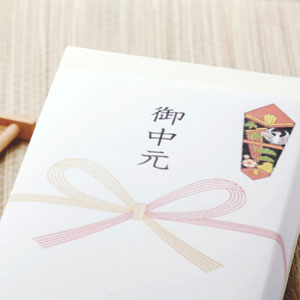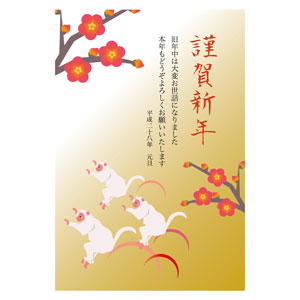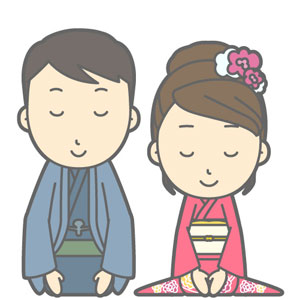今年は身内の不幸があったから年賀状は出さない代わりに
喪中はがきの準備をはじめたけど
喪中の範囲は親族のどこまででしょうか?
祖父や祖母、叔父や叔母の場合など迷いますよね。
身内で話し合っても意見が違いまとまらないこともあります。
また喪中はがきはいつまでに出せばいいのでしょうか?
そこで年賀状の喪中の範囲や喪中はがきを出す時期と
その文例についてまとめてみました。
年賀状の喪中の範囲 祖父や祖母、叔父や叔母の場合は?
喪中はがきは喪に服するために新年の挨拶を欠くことを予め事前に知らせるための年賀欠礼の挨拶状のことです。
迷うのは近親者で不幸があった場合にどこまでが喪中なのかということですよね。
年賀状の喪中の範囲は親族のどこまででしょうか?
それは故人との関わりや本人の気持ちにもよるところですが、一般的には二親等までなります。
- 一親等・・・両親・配偶者・子・配偶者の両親
- 二親等・・・兄弟姉妹・配偶者の兄弟姉妹・祖父・祖母・孫
- 三親等・・・伯父・伯母・叔父・叔母
両親、配偶者やその両親、子供などの一親等に、兄弟姉妹や配偶者の兄弟姉妹、さらに祖父祖母などの二親等までの場合は喪中はがきを準備します。
また、叔父や叔母の場合は三親等にあたるので一般的に喪中の範囲ではないことになりますが、これは一般的な場合であり、故人との関わりや本人の気持ち次第では例外もありえますので、厳密に決めることは難しいといえるでしょう。
その辺りは親族(主に両親や配偶者の両親などに)で相談したり話し合ったりするのが一番良いと思います。
年賀状の喪中ハガキを送る時期はいつまで?
喪中はがきを送る時期はいつまででしょう。
喪中はがきは年賀欠礼の挨拶状ですので、年内に届けば問題ないというのが一般的です。
しかし毎年年賀状を送られる相手の方は、喪中であることを知らないまま、いつも通りに年賀状の準備をされてしまいます。
せっかく年賀状を用意してもらってから喪中のはがきが届いては申し訳ないですよね。
そうなると相手の方が年賀状を準備する前には届くように送るのがいいでしょう。
時期としては11月中旬から、年賀状の受付が始まる前、遅くても12月初旬頃までには届くようにしましょう。
年賀状の喪中ハガキの書き方や文例を紹介!
喪中はがきの書き方や文例をご紹介します。
はがきを書く際のポイントは以下の3点です。
「喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます」
まずは喪中のため新年のご挨拶を遠慮する旨を伝えます。
2 誰がいつ亡くなったのか・・・
「本年○○月に父○○が永眠いたしました」
次に誰がいつ亡くなったので喪中なのかを書きます。
3 故人が生前お世話になった御礼や挨拶・・・
「ここに本年中賜りましたご厚情を深謝いたすと共に明年も相変わらぬご厚誼のほどをお願い申し上げます」
最後に生前の御礼やご挨拶で締めくくります。
まとめ
年賀状の喪中の範囲や喪中ハガキを送る時期がいつまでなのか、またその喪中はがきの書き方のポイントや文例をご紹介しました。
喪中ではこちらからの新年のご挨拶を遠慮するため、相手も今年は年賀状を送らないというのが一般的です。
しかし、年に一度のご挨拶でしばらく会っていない方からの年賀状は受け取りたいという方もいらっしゃいますよね。
その場合、年賀状を受け取ったとしてもマナー違反にはなりませんのでご安心を。
その際は「皆さまから頂く年賀状は励みにもなりますので、例年どおりお送りくださいませ。」という感じで一言添えるといいでしょう。