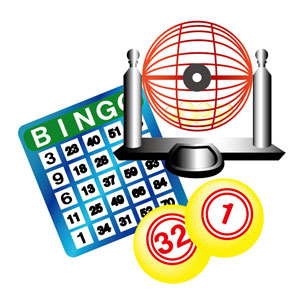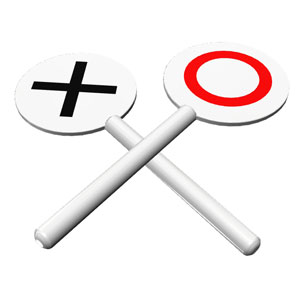節分の豆まき

2月は節分ですね。
幼い頃は節分の日ともなると、家の中や外に向かって「鬼は外、福は内」と豆まきをしたことを思い出します。
そんな節分の豆まきですが、物心がついたころからなんとなく参加していて、詳しいことは知らないという人も多いですよね。
節分の豆まきの由来や意味、正しい作法について、また節分に食べる恵方巻と豆まきはどちらが先かということについてご紹介します。
節分の豆まきの由来や意味は?
節分の豆まきの由来や意味についてご紹介します。
節分の豆まきの由来は?
節分や豆まきの由来についてご紹介します。
節分とは、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のことを指します。もともとは季節を分けることから節分とされ年に4回ありますが、立春の前日の節分は節切月日の大晦日にあたり立春を1年の始まりととらえるとその前日の節分は特に重要視されました。
豆まきの由来は、季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると考えられ、それを追い払うための行事が執り行われたことが始まりです。
もとは中国の習俗が伝わったものとされ、鞍馬山に出てきた鬼をお告げによって、鬼の目に大豆を投げつけて鬼を退治したという話があり、それが始まりと言われています。
節分の豆まきの意味は?
節分では、なぜ豆をまくのでしょうか?
豆などの穀物にはもともと生命力と魔除けの呪力が備わっているという信仰があったことがポイントです。
語呂合わせによると豆は魔目または魔滅とされ、鬼の目に投げつけて鬼を滅するという意味があり、魔除けの呪力が備わっていることから、豆を鬼にぶつけることで鬼を滅することは、邪気をを追い払うという意味があります。
また豆は生命力があることから、撒かれた豆を自分の年(数え年)の数だけ食べることで、この一年は病気にならず健康で元気でいられるように願うという意味があるのです。
節分の豆まきの正しい作法は?
節分の豆まきの正しい作法をご紹介します。
節分の豆まきなどの季節の行事は地方によっても異なることがありますが、この節分の豆まきについては各家庭によっても違いがあることがあります。
- 福豆(炒った大豆)を用意します。
福豆は炒った大豆のことです。豆を炒って豆まきをするまでは枡や三方に入れ神棚に供えます。 - 豆まきは夜になってからする。
鬼は夜にくることから、豆まきも夜に行います。 - 一家の主人が豆を撒く。
本来は一家の主人がするべきですが、家族全員で行いましょう。 - 「鬼は外!福は内!」と言って豆を撒きます。
奥の部屋から順番に部屋の窓を開けて「鬼は外」と豆を撒いて、鬼が戻って入らないように窓を閉めた後に今度は「福は内」と部屋の中に撒きます。 - 豆を撒いたら豆を食べる。
1年の厄除けを願いながら、自分の年齢よりも1つ多く豆を食べましょう。
節分の豆まきは恵方巻との順番はどっちが先?
節分の日は豆まきだけでなく、恵方巻も食べますよね。
そこで疑問に思うのは同じ日に豆まきと恵方巻どっちを先にすればいいのでしょうか?
豆まきは鬼が夜にくることから夜に行います、では恵方巻はというと実は恵方巻も夜なんです。
恵方巻は節分の夜に、その年の恵方に向かって願い事を思い浮かべながら、無言で太巻きを丸かじりします。
そこで同じ夜にどっちを先にすれば良いのかとなりますが、実は厳密な決まりはありません。
現代では、どちらも節分のイベントのようなものです。
夕飯の前に豆まきをして、夕飯はその年の恵方に向かって恵方巻を丸かじりしていいわけです。
まとめ
節分の豆まきの由来や意味、また正しい作法や豆まきと恵方巻の順番についてご紹介しました。
節分の豆まきは、大人になると中々行う機会も少ないと思いますが、久しぶりに行ってみるのもいいかもしれません。
今年も良い年になるといいですね。