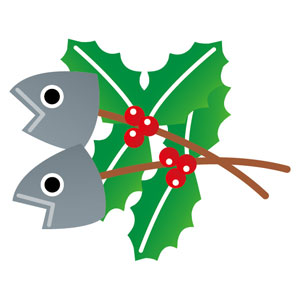
節分のいわし
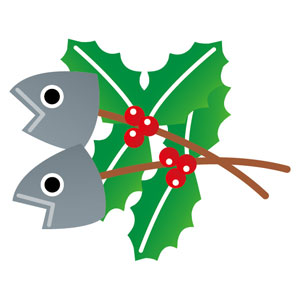
節分ときくと、最初に思い浮かぶのは豆まきですよね。
最近は恵方巻もあります。
でもいわしが節分に関係あることはご存知でしたか。
地域によっては節分の日にいわしを食べたり、また鰯の頭をヒイラギに刺して(柊鰯)玄関や軒先に飾ったりします。
そこで節分にいわしを食べる由来や柊鰯の作り方やいつまで飾るかについてご紹介します。
節分のいわし 食べる由来は?
節分に食べるものは豆や恵方巻ぐらいと思っていると、地域によっていろいろなものが食べられています。豆、恵方巻き、蕎麦、いわしなどです。
この「いわし」は主に西日本で食べる習慣がありますが、なぜ節分に「いわし」を食べるのでしょうか?
「いわし」は漢字では「鰯」魚へんに弱いという字です。これは「いわし」という魚がすぐに死んでしまうからというのが一般的ですが、他に(いわし=いやしい)卑しい魚であることが転じたという説もあります。
この弱く卑しい「いわし」を食べることが体の中の鬼を追い払うということや、焼いている時の臭いや煙を鬼が嫌がるので鬼を近寄らせない、また邪気を払うという意味があります。
また、節分は本来年に4回、季節の始まりの前日のこと。立春の前日の節分は今の大晦日のようなもので、春になる前に魔除けの意味で「いわし」を食べるということです。
節分のいわし 柊鰯とは?作り方は?
柊鰯(ひいらぎいわし)とは
節分のいわしは食べることだけではありません。魔除けとしても門口に飾る柊鰯という風習があります。
節分に魔除けとして柊の小枝に焼いた鰯の頭を刺し、それを門口に飾ったもので、地域によっては見かける節分の風習です。
柊の葉の棘が鬼の目を刺すので鬼が入ってこられず、「いわし」を焼いた臭いと煙で鬼が近寄らないといわれています。
柊鰯の作り方は
では、この柊鰯はどのようにつくるのでしょうか?動画でご紹介します。
焼いた鰯の頭に柊の小枝を鰯の目にに向かって刺すだけです。
簡単ですよね。
節分のいわし 柊鰯はいつまで飾る?そのあとの処分方法は?
柊鰯はいつからいつまで飾る?
柊鰯はいつから飾りはじめ、いつまで飾るのでしょうか。
柊鰯を飾るのは、一般的に節分の当日ですが、地域によっては小正月が過ぎた頃(1月16日)から飾るところもあるようです。
また、いつまで飾るのかというと、節分の翌日までという場合や、2月末まで、また1年間とこれも地域や家庭により様々です。
はずした柊鰯の処分方法は?
はずした柊鰯はその後どのように処分すればいいのでしょうか?
さすがに、ゴミ箱に捨てるのは躊躇ってしまう柊鰯ですが、一番手軽な処分方法は、塩で清めてから半紙に包んで捨てるという方法です。これなら、はずしたタイミングでできますからいいですよね。
本格的な処分は、神社のお焚き上げに持参するという方法です。これは神社によっても受付してくれるところとそうでないところがありますから確認が必要です。
柊鰯は鬼から家を守ってくれた魔除けですから、そのままゴミとして処分するのは避けましょう。
まとめ
節分にいわしを食べる由来や柊鰯の作り方、また柊鰯はいつからいつまで飾り処分はどうすればいいのかについてご紹介しました。
節分は豆まきのイメージが強いですが、今年はいわしにも注目したいですね。
いわしを食べて、柊鰯を作って飾れば今年はいい年になりそうな気がします。





