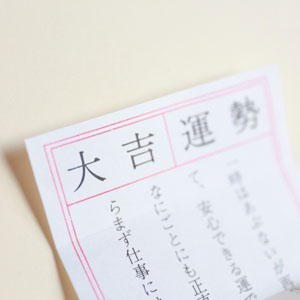毎年お正月に初詣に行くけど、出掛ける日はその年によってもいろいろ。
元旦に行く年もあれば、親戚が来るのを待って三が日に行ったり、三が日が過ぎて松の内に行くこともあります。
初詣はいつまでに行けばいいのでしょうか?
もともと初詣の意味や由来って?
そこで初詣はいつまでに行けばいいのか、その意味や由来について、また正しいお参りの仕方についてご紹介します。
初詣はいつまでに行けばいい?
初詣はいつまで行けばいいのでしょうか?
諸説ありますが、初詣にいつまでに行けばいいのか厳密な決まりはありません。
元旦や三が日はもちろん、松の内(1/7まで)に行けば大丈夫というのが一般的です。
しかし神様への新年のご挨拶ですから、早いに超したことはありません。遅くても松の内までには行くのがいいでしょう。
正月の松飾りのある期間のことで、松の内の始まりの日は12月13日から、また終わりは関東地方では7日まで、関西地方では15日までとなります。
初詣の意味や由来は?
初詣の意味とは?
初詣は、神社やお寺などに「初めて」「詣でる(もうでる)」ことです。 「詣でる」とは、「自分の意志で行くこと」をいいます。
初詣の意味とは、新年に初めて自分の意志で神社やお寺に行き一年の感謝を捧げたり新年の無事と平安を祈願したりすることになります。
初詣の由来とは?
元々は「年籠り」といって家長が祈願のために大晦日の夜から元日の朝にかけて氏神の社に籠る習慣があり、その年籠りが大晦日の夜の「除夜詣」と元日の朝の「元日詣」との2つに分かれ、元日詣が今日の初詣の原形になりました。
江戸時代末期までは、氏神様に参詣したり、恵方にあたる社寺に参詣(恵方詣り)したりしていましたが、この元日詣が習慣化するのは明治中期のことで、その後は氏神様や恵方とは関係なく、有名な寺社に参詣することが徐々に一般的になっていきました。
初詣のお参りの仕方は?
初詣のお参りの仕方にもマナーや作法があります。
これからもお参りに行くことはありますので、神社でのお参りの仕方をご紹介します。
<神社でのお参りの仕方>
これから神様に新年のご挨拶をするので身なり、服装の乱れを整えましょう。
神社では、神様を敬う気持ちを表わすため軽く会釈をしてから境内に入ります。
境内に入ったら、神前に進む前に手水舎で身を清めます。
- 右手に柄杓(ひしゃく)を持ってまずは左手を洗い清めます。
- 柄杓を持ち替えて今度は右手を清めます。
- 再度柄杓を右手に持って左の手の平に水を注いでその水で口をすすぎます。柄杓に直接口をつけるのは他の方の迷惑になるので注意しましょう。
- 今水を注いだ左の手の平を清めます。
- 柄杓を縦にして自分が持った柄の部分を水で流し、きれいにして元の位置に伏せてもどします。
いよいよお参りです。手順に従って姿勢を正して行います。
- 神前に進んで、姿勢を正しくします。
- 賽銭箱に賽銭を入れます。
- 鈴を鳴らします。
- もう一度姿勢を正しくします。
- 二拝二拍手一拝の作法で拝礼をします。
胸の前で2回拍手をします。
もう一度90度の礼で1回おがみます。
最後に向き直って、軽く会釈をしてから境内を出ます。
※寺院では手を合わせ合掌するだけで拍手はしませんので、間違わないようにしましょう。
まとめ
初詣はいつまでに行けばいいのか、またその意味や由来とお参りの仕方についてご紹介しました。
初詣はいつまでに行くという厳密な決まりがありませんので、もし松の内を過ぎてしまって行こうかどうしようかと迷われるなら行かれた方がいいでしょう。
一度神様に新年のご挨拶をすれば、その後は清々しく過ごせると思います。
ご家族なら毎年初詣に出掛ける日を決めておくというのも迷わないでいいですよね。
新年は良い年になるといいですね。